こんにちは、「やす」でございます。
今回は現役の地方公務員(役所勤務)である私が“民間での人事職の経験”と“自己理解プログラムで学んだストレングスファインダーの知識”を掛け合わせて、
「事務系の地方公務員に向いている才能」をストレングスファインダーの資質別にまとめてみたいと思います。
あくまでも、わたくし「やす」の独断と偏見ですので、コメント・ご意見をどんどん加えて頂いて、皆さんと一緒にアップデートできればと思いますのでよろしくお願いします。
目次
そもそもストレングスファインダーとは
クリフトンストレングス®(ストレングスファインダー®)とは、米国ギャラップ社の開発したオンライン「才能診断」ツールです。Webサイト上で177個の質問に答えることで、自分の才能(=強みの元)が導き出されます。クリフトンストレングス®(ストレングスファインダー®)における「才能」は次のように定義されます。
『無意識に繰り返し現れる思考、感情、行動のパターン』
すなわち、自分の思考、感情、行動の「特徴」そのものが「才能=強みの元」だと言うのです。(公式サイトより)
ストレングスファインダーは結構有名ですよね。昔、新卒2年目の時に本を買って才能診断を受験したことがあります。(その当時はどう活かしたらいいのか、よく分からず役に立ちませんでしたが…)
ストレングスファインダーが定義する「才能」は全部で34つの資質に分類されています。この記事で全部は紹介しませんが、検索すると出てくるので気になる方は見てみてください。
それでは「本題」にいきましょう!
地方公務員を目指している人に伝えたい「向いている才能」5選
民間から地方公務員に転職してみて、まず感じたのは「同じような人たちの集団だな」ということです。みんな平均的に地頭は良いですし、同じような安定志向を持ち、争いを好まず、真面目な人が多いので特段大きな問題は起きません。粒が揃っていて、日々働きアリのように仕事が回っています。
それもそのはず、地方公務員は数年おきに必ず異動があるので、どんな課に配属されたとしても、与えられた仕事を着実にこなさなければいけないからです。
だから、悪い言い方をすれば、どんな業務やポジションを与えられてもすぐに覚えて、問題なく仕事を回すことができる能力が一定以上ある「代替可能」な人たちで組織を構成する必要があるんですよね。
(その分、肌に合わない人は耐えられずに辞めていきます。まあ、これは才能だけではなく、価値観も関わった問題ですかね…。)
【独断と偏見!多くの公務員が共通して持つ「価値観」についてはこちら⇓※近日公開予定】
そんな集団に属してみて、共通してみんな持っているなと感じた「才能」を今回は厳選して5つ紹介していきます!
紹介していく「才能」の中には「民間企業でも必要でしょ。」と思うものもあるかと思います。もちろん、公務員も同じ“社会人”ですので当然あるかと思います。
では順不同で紹介していきます。
①規律性(★★★★☆)
お伝えし忘れていましたが、ストレングスファインダーでは34の資質を4つのグループに大別しています。
- 実行力グループ
- 影響力グループ
- 人間関係構築力グループ
- 戦略的思考力グループ
規律性は“実行力グループ”に属し、構造化と計画性に関する資質です。
一言で表すと「安定と秩序を好み、ルーティンや規則を重んじる」です。
まさしく、イメージする公務員っていう感じがしますよね。
実際、働いてみてその通りだと思います。法改正や世間で話題になっている時事ネタ(例えば、カスハラ問題等)に対応する以外は基本的に前年度にやった業務を今年度も行います。
国や県から依頼される調査物も毎年ほぼ同じ内容で、同じ時期に送られてきます。提出物も前年に回答した内容をほぼ書き写すだけです。(念のため申し上げますが、窓口対応とかイベント行事とかクレーム対応とか、ルーティンワーク以外の仕事もたっくさんあります!!!!!)
ただ、そういったルーティン的な仕事も量がとても多いため、効率良く捌いていく必要がありますし、異動直後だと、何から手を付けていいのか分からないといった状況に陥ります。
そういった際に、「規律性」という才能は、限られたリソースの中で雑然とした物事を整理して、期日までに終わらせるための計画を立て、効率的に実行するという所に役立ちます。そして、ルーティンに仕上げてしまう力があります。
逆に苦手とする領域は「直感」や「大きな変化(混乱)」です。マニュアルや規則が無い問題に対して苦手意識を持つ人が多いです。
規律性が資質の上位にくる方は「しっかり」「ちゃんと」「きちんと」という言葉をよく使いがちかもしれないです。
ちなみに、規律性と対極的なのが「適応性」や「アレンジ」という資質です。これらは変化を好む資質です。
②公平性(★★★★★)
公平性も“実行力グループ”に属し、ルールや平等に関する資質です。
一言で表すと「ルールや手順に従い、公平に物事を実行することができる」です。
また、「個人より全体」「均一性」「一貫性」「標準的な手順」がキーワードになり、手順に従った繰り返しの作業や淡々とした作業に向いています。
わかりやすく言うと「いつも、この手順でしてきた。」「みんな(他の自治体)はどうしてる?」と言うタイプですかね。
これも、まさしく公務員のイメージ通りだと思います。公務員は特定の個人に向けてではなく、全体に対する奉仕者であり、法律や条例に従って平等に仕事をしています。
業務もマニュアル化されていたり(されていないのも結構ありますが。というか、あってもどこにあるのか探すのが大変。)するので、それに従って、淡々と仕事をすることが苦痛ではない人は公務員に向いていると思います。
また、公平性タイプは抜け駆けされるのも、するのも抵抗があります。私が勤めている自治体も国や県からお達しがきたら、まず周辺の自治体と足並みを揃えようとします(周辺の自治体も同様なので、みんなでお互いをチラチラ見ながら進んでいきます)。
これに対極的な資質が「個別化」です。「個別化」は全体ではなく一人ひとりに着目し、オーダーメイドが得意な資質です。
③慎重さ(★★★★★)
慎重さも“実行力グループ”に属し、準備やリスク管理に関する資質です。
一言で表すと「無駄な問題(失敗)を起こさずに、着実に物事を実行できる」です。
はい。これもまさしく公務員向きですね。
キーワードは「安全第一」「準備万端」「安心」が挙げられます。
公務員の仕事は世間から見ても“できて当たり前”、“間違ってなくて当たり前”という風潮がありますし、それは職員同士でも共通認識であります。
批判されないように、重箱の隅をつつくように、日々仕事をしています。例えば、文書を作成するときは、ゴシック体や明朝体、先頭行のズレ、文字の大きさなど様々なところをチェックします。それに、リスク管理能力もみんな高いです。後付け説明がしやすいように「〇〇等」を乱用します。
公務員の仕事は基本的に決裁が下りないと実行できないようになっています。たとえ、職場内で他課から依頼されたちょっとした調査物でさえ、簡易決裁に通して、それが下りないと勝手に回答することはできません。
なぜなら、その解答は所属課を代表して回答することになるため、もし回答が間違っていると所属課の責任になるからです。だから、どんな些細なことを依頼されても、基本的に決裁をとって、所属課の人たちに見てもらって、問題がなければ他課へ回答するといった流れになっています。
リスク管理すごいですよね。最初、入庁した頃は「え?こんなのも決裁とらないといけないの…?効率悪すぎ…。」とよく思っていました。
決裁は電子決裁もありますが、まだまだ紙社会です。
印刷した決裁書とその説明資料は決裁板(バインダー)に挟んで、主事→主査→係長→副課長→課長(→部長→…)のように回って行きます。一日にいろんな人の決裁が自分のところにも回ってきます。時には全然関与していない業務内容の決裁まで。課長や部長の仕事って大変そうだな…と感じます(小並感)。
そんな慎重さに対極的な資質が「ポジティブ」「自我」「活発性」です。
あなたは物事に取り組む際、「やってみないと分からない」というタイプですか?それとも、やる前に可能な限り失敗の芽を潰しておきたいタイプですか?もし、後者なら公務員に向いているかもしれません。
④調和性(★★★★☆)
かなり長い記事になってしまいました。
紹介する資質は残り2つです。
調和性はこれまで紹介した実行力とは違い“人間関係構築力グループ”に属し、合意や着地点に関する資質です。
一言で表すと「異なる意見の中から一致する点を探ることができる」です。
平和的で衝突を好まない、落ち着いた人が多い印象です。個人の思惑よりも、全体の調和を望むタイプです。
全体の奉仕者として、自治体独自の施策を打ち出す場合や道路工事をしようとしても必ず反対意見が出てきます。また、職場内で新しい取り組みを実施する際も「慎重さ」の資質を持つ公務員たちの間では「〇〇というリスクがある」「~という場合はどうする」など様々な意見が出ます。
そういった際に、周囲の意見を聞き、適切に合意を取りつつ、後戻り無く前進させていく力があるのが調和性タイプの持つ力です。
公務員の中でも根回しを特に上手にできる人は「調和性×戦略性」の組み合わせかもしれないです。
ちなみに、公務員試験では「調整力」をアピールすると、とても評価されます。この調整力(=コミュニケーション能力)が、まさしく「調和性」の資質だと思います。
実務でかなり重要になってくる資質ですので、調整力に自信がないという方は公務員になってから少々苦労するかもしれません。
⑤適応性(★★★☆☆)
いよいよ最後の資質、「適応性」です。
適応性も“人間関係構築力グループ”に属し、環境変化、マルチタスク、順応に関する資質です。
一言で表すと「コトが起きたならしょうがない。やるか。」というタイプです。
キーワードは「対応力」「ギアの入れ替え」「状況打破」が挙げられます。
「え?環境変化?順応?さっきまで、ルーティンとか一貫性って書いてたよね。」と思われた方も多いかと思います。
しかし、公務員にとって適応性もある程度、上位に持っていた方が良い資質であると言えます。
その理由はこの5つです。
①異動の多さ
②窓口対応でどんな人が来るか分からない
③国や県から急に重たい仕事が降ってくる(期限キツキツの調査物や解散による選挙等)
④急に同じ課内や係の同僚が休職する
⑤地震や洪水などの天災が発生した際の対応
どれも予測不可なものばかりです。
どんなに理不尽な内容であっても、人員が足りなくなっても、与えられた仕事は着実にこなさなけばなりません。全体の奉仕者である公僕の宿命です。
①の異動なんて、これまでと同じ課内で所属する係が変わっただけで仕事内容がガラッと変わります。課を跨ぐ異動となると、今まで図書館で仕事してたのに、4月1日から急に生活保護関係の仕事(ブラック)なんてことも、全然あり得ます。
④の休職に関して、適性が無い仕事をやらされるせいで、仕事が思うように進まず、メンタルに負荷が掛かり休職する職員が多くいます。さらに、政治家による公務員減らしや、就活市場における公務員の不人気もあり、限られた人員の中で個人商店のように、他に頼れる事もなく、ひとりで何個も仕事を抱えてマルチタスクをしている現実があります。
だから、これまで紹介した資質と相反するような「適応性」も併せ持っている必要があります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
この記事を最後まで読んでいただくと分かるように、公務員にはオールラウンダーが求めらめています。
際立った能力がなくても、何でも器用に問題なくこなせる人です。
イメージを分かりやすく伝えるとレーダーチャートが平均以上で綺麗に整っている人ですかね。
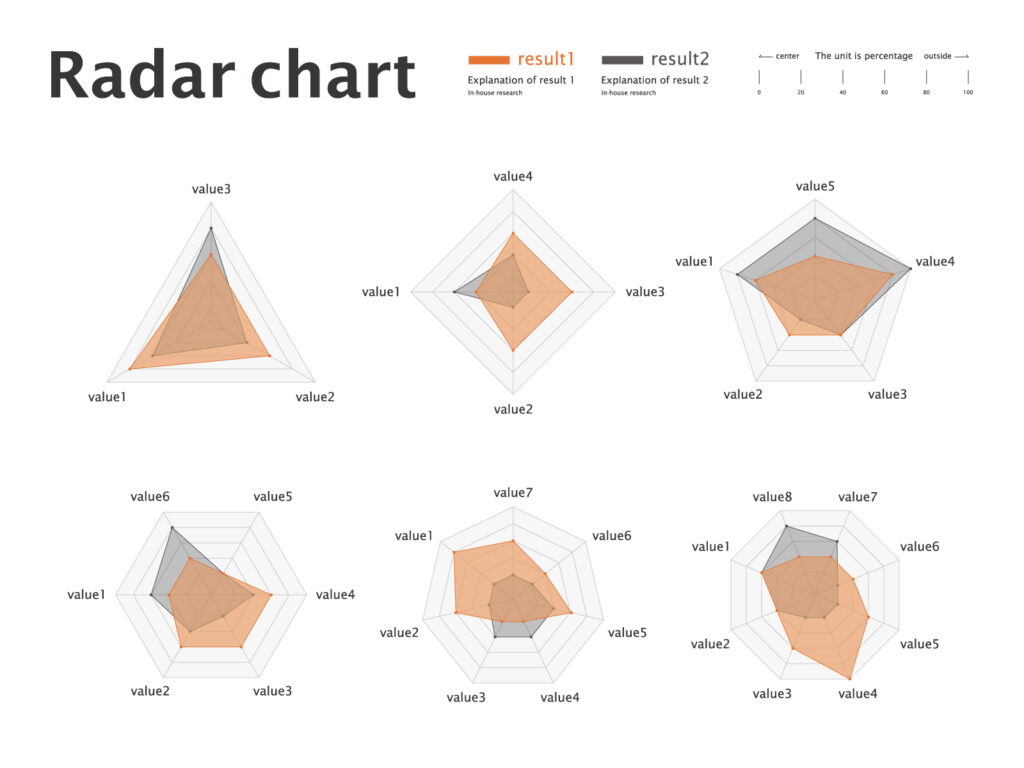
その中でも、特に調整力に優れていたり、飲み込みと応用のスキルが優れていたりすると「スーパー公務員」と呼ばれ、職場内でも重宝される存在になります。
また、今回紹介した資質5つは、単体ではなく、それぞれ掛け合わさって発揮することが前提となります。
ここで私のストレングスファインダーの結果を紹介すると、このようになります。
- 慎重さ・・・3位
- 適応性・・・6位
- 調和性・・・11位
- 規律性・・・21位
- 公平性・・・26位
その人が持つ資質の内、上位資質だと言えるのは、10位周辺までです。
入庁してみて割と序盤で、自分あんまり公務員には向いていないなと感じました。
でも、それは資質だけでなく、自分の価値観にもマッチしていないと感じたからです。
次回は、公務員に向いている価値観について独断と偏見でまとめてみようと思います。
長い記事でしたが、最後までご覧いただきありがとうございました!!
では、今日はここで終わり!

